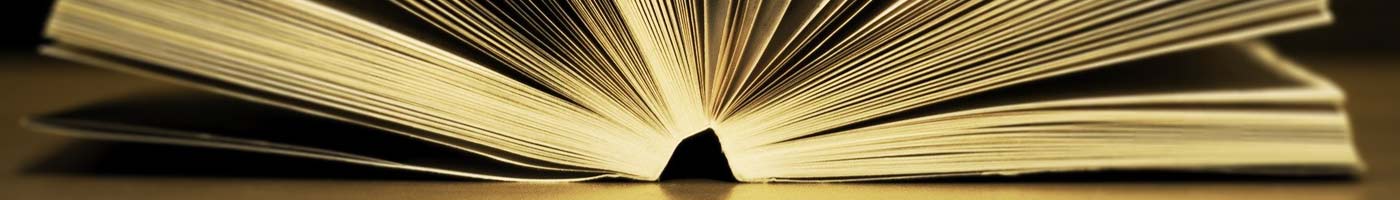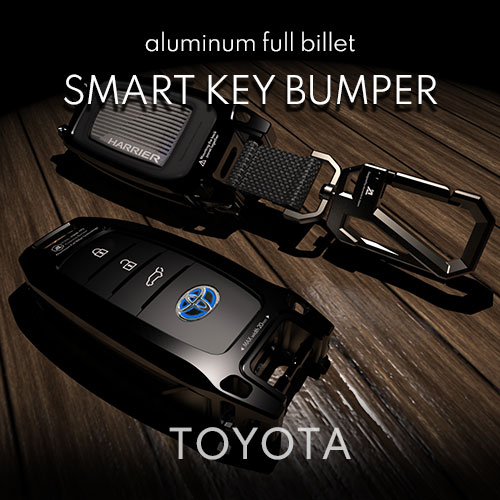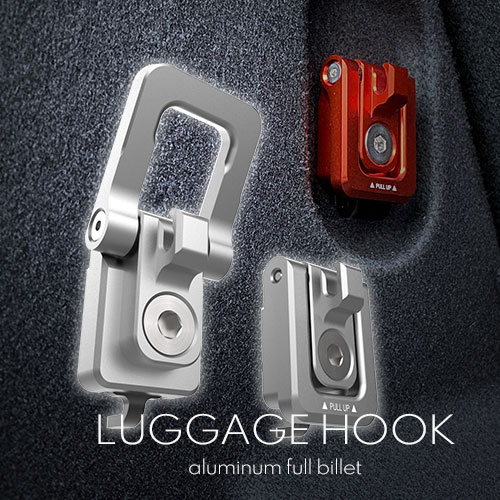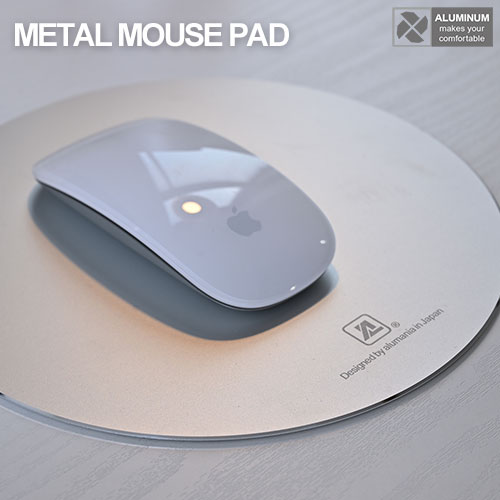ここではノギスの中で最も多く目にする、150㎜目盛り式のノギスの使い方について、初めて使うような初心者向けに、基本的な使い方(測り方)と測定値の見方(読み方)について解説していきます。
ノギスとは?
ノギスとは、物体の「幅」「高さ」「深さ(段差)」を0.05㎜(5/100㎜)単位まで測ることができます。※0.05㎜は目盛り式の場合

ものづくりの現場では欠かせないノギスは、ご家庭でも一つは用意しておけば損はしない、測定器の中でも手軽で万能な一生モノともいえるツールです。
ノギスには、測定したい箇所別に3箇所の測定する部分があります。それらを利用することで、主に「物体の幅(内径と外径)」・「段差(高さや深さ)」に分けて測ることが出来ます。
最初にノギスのそれぞれの名称とその役割(機能)について見ていきましょう。
ノギスの主要部分名称とそれぞれの機能解説
ノギスといえば「ミツトヨ」が有名です。他にもシンワや新潟精機などありますが、ここで使用しているノギスはミツトヨ製ノギスをベースにしたイラストで解説してきます。
測定するときに使用する部分は3箇所
- 内側ジョウ(クチバシ)=内径・内寸測定用
- 外側ジョウ=外径・外寸測定用
- デプスバー=深さ・高さ測定用

このノギスのイラストを利用したい方はこちらからsvgデータをダウンロードしてください。
イラストは商用問わず自由にご利用いただいて構いませんが、利用者側で生じる全ての責任は負いません。
目盛りは主尺と副尺がありスライダーを移動させます。
- 主尺目盛り=1mm単位を見る
- 副尺目盛り=最大0.05㎜単位を見る
- スライダー=ジョウ・デプスバーを動かす部分
ノギスが動かない時の確認箇所

スライダーが動かせない場合はロックがかかっている場合があります。親指で簡単にスライドできない時はつまみネジ部が締まっていないか確認してください。
例)ノギス(ジョウとデプスバー)の測り方
ここでは段差も測定できるデプスバーのポイントを知るために、「高さ」と「深さ」に分けて解説しています。寸法の読み取り方はこの章の後に説明します。
解説用の題材としては、内側がくり抜かれた形状の【外側】横幅W1と縦幅L1、【内側】の内横幅W2と内縦幅L2、【高さ・深さ】の深さDと高さHを測定することとして解説していきます。

【外側】を測る方法 外径(外寸)・ 外側ジョウ

外径を測定するときは、外側ジョウを使用します。
スライダーを動かして対象物の外から挟みます。 球の外径も測定でき、ノギスの使い方の中でも最も利用する測定方法になります。(題材のW1とL1がこれで測定できます。)

【内側】を測る方法 内径(内寸)・ 内側ジョウ

内側を測るときは内側ジョウを使用します。
測定したい対象物の内径に入れて、スライダーを使って内側ジョウを広げます。穴の内径を測る場合も同じです。 (この方法で題材のW2とL2がこれで測定できます。)

【高さ】 を測る・ デプスバー

高さを測るときはデプスバーを使用します。
ノギスのエンド部分を上面に当てて、スライダーを動かしてデプスバーを地面に押しつけます。 (この方法で題材のHが測定できます。)

ノギスの可動範囲内に収まる測定物であれば、高さは外幅の測定方法で行ったほうが確実で正確性が上がります。
【深さ】を測る・ デプスバー
深さを測るときも、高さの時と同じようにデプスバーを使用します。
ノギスのエンド部分を上面に当てて、スライダーを動かしてデプスバーを内底に押しつけます。 (この方法で題材のDが測定できます。)

この時、内側にRなどがある場合はデプスバーの切り欠きを利用します。底がRや斜めになっている場合に逃がしてあげることができるため、底が角でない場合に役立てます。
測定した値(主尺と副尺)の読み方

最終的には主尺目盛りと副尺目盛りの線が一直線上に並んで(合致して)いる部分を探して数値を読み取る必要があります。
必ず上下の目盛り線が並んでいる箇所ができます。
基準合わせの確認
測定する前には、必ずノギスを閉じて「主尺目盛りの0の線」と「副尺目盛りの0」がぴったり合っていることを確認してください。
ここで0が合っていないと測定値はズレて表示されることになり、正確な値ではなくなるためです。ノギスを落としてしまったとき、曲げてしまったら確認、基準位置が0で合致するか確認は必要です。

「デジタルやダイヤル式ではない」ここで使用している一般的な目盛りのノギスから寸法を読み取る場合は少し読み取りにくい点があります。
寸法としての数値を算出する(読み取る)ためには、以下から紹介するステップで数値を小数点などの段階をそれぞれで読み取っていく必要があります。
測定手順(外側ジョウの場合)
- スライダーを移動させて測定物を挟む
- 副尺目盛りの0の線の位置を見て主尺目盛の数値を読み取る(1mm単位)
- 副尺目盛の中で主尺目盛と一直線上にある線を探す(0.1mm単位)
- 副尺の数字間の短い線の方が一直線上に近いか確認(0.05㎜単位)
- それぞれの単位の数値の合計が測定値になる
測定数値=【1㎜単位の値】+【0.1㎜単位の値】+【0.05㎜単位の値】
六角ナットを外側ジョウで挟んだイメージで、ここでの測定値を読み取っていきます。

1. 1mm単位を見る
1㎜単位(整数値)の数値を確認します。
副尺目盛りの0の位置が測定値の整数値になります。(副尺目盛り)0が指す主尺目盛りの数値を読み取ります。ここが少数点以下ではない整数の値になります。

副尺目盛りの0の位置が主尺目盛りの23と24の間にあります。ここでは1mmの単位が23mmとなります。
2. 0.1㎜単位を見る
0.1㎜単位(小数点第一位)の数値を確認します。
副尺目盛りの数字と主尺目盛りの線(上下の線)が揃っている位置を探します。合致している副尺目盛りの数値を読み取ります。これが少数点以下の値になります。

副尺目盛りの数字の上の線が、主尺目盛りの線と合致している部分を探していきます。この場合は7が最も近くなっており、8では離れていっています。そのため、最も近い7の値が0.1㎜単位の結果であり、ここでは0.7㎜の意味になります。
3. 0.05㎜単位を確認
0.01㎜単位(小数点第二位)の数値を確認します。
※今回使用している目盛りノギスの場合は0.05㎜単位になります。
数字と数字の間に短い線があります。ここは0.05㎜単位になっており2番の0.1㎜単位を見た時と同じ様に、短い線も主尺目盛りの線と合致しているかどうか判別します。この短い線が主尺目盛りと重なっていれば、小数点2位がプラス+0.05になります。

測定値は 【1㎜単位の値】+【0.1㎜単位の値】+【0.05㎜単位の値】になりますので、
ここでの例の場合は、【23】 +【0.7】 +【0.05】 = 23.75㎜となります。
ノギスの使い方まとめ
ここまでの内容で「ノギスの使い方」を簡潔にまとめておきます。
- ノギスの測定部分は「内側用」と「外側用」のジョウと「デプスバー」
- スライダーを動かして使用する( 動かない時はロックが締まっている)
- 対象物の高さはノギスの可動範囲内にあれば外幅で測定する
- 測定寸法は副尺目盛りと主尺目盛りの線が合致している部分を探して読み取る
- 1㎜の値+0.1㎜の値+0.05㎜の値の合計値が測定寸法になる
ノギスは手軽に正確に測定できるものですが、大きさとしてはせいぜい200㎜くらいまでになります。一般的なノギスは使い勝手の良い150㎜までとなります。
この記事をシェアする
この記事の前後リンク
- 個人情報やプライバシーを侵害するような情報
- 閲覧される他の方に不快を与えるような内容や他の方に対しての暴力的な言葉や中傷
- 著作権の侵害・法律や倫理に反する行為
- 個人的に偏ったご意見や見解、他社を含む商品・サービスの不平や不満
- 個別記事の初期投稿日から一定期間を過ぎ、コメント投稿を受け付けていない場合
- 商品の感想または不具合など、個々に対応する必要がある案件
- 個々の記事に関係のない内容や話題の乱雑な投稿、迷惑なオフトピック
- その他、投稿時期のAI判別による不正防止と時事的な内容に抵触する場合など