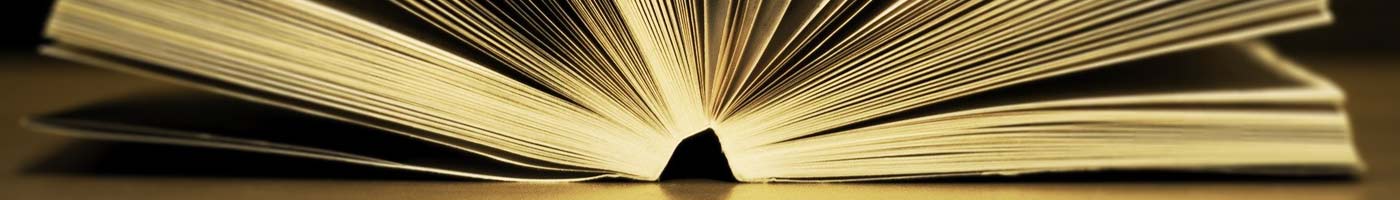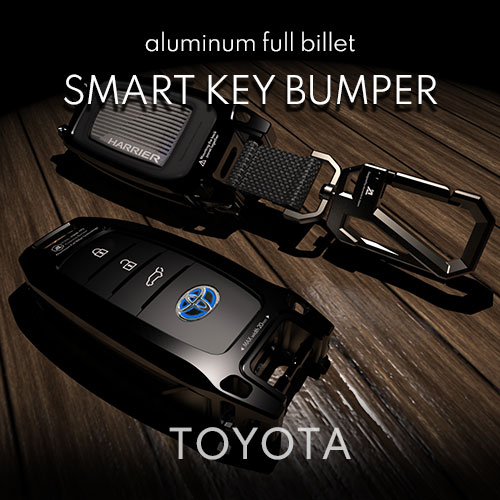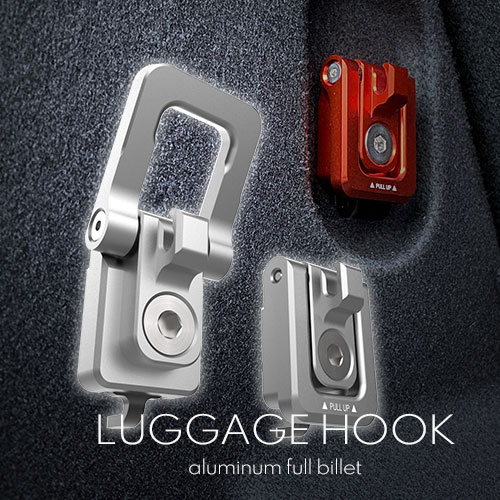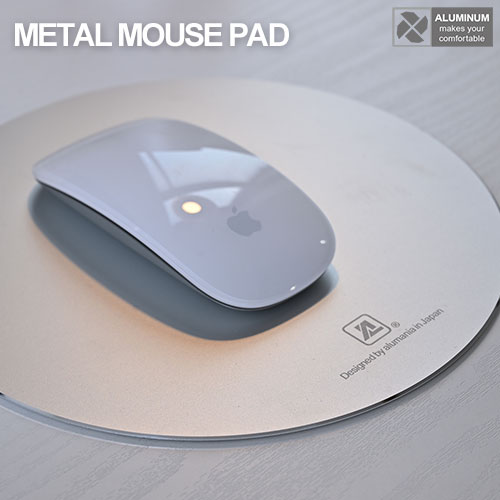六角ボルトの詳細サイズを確認する前に、まずJIS規格には「部品等級」としてABCの種類があります。部品等級はそのネジの頭からネジ部など生産する精度別に分かれます。
また、ネジ部の精度で表記される古くなった等級があり、混乱しやすくなっています。ネジ部の精度は過去には「1~3級」と数字で表していましたが、現在の主流はISOに準じて、6H,8gのように記載されています。
全体を形成するためのネジの生産精度としての”部品等級”はアルファベットのABCで、ネジ部の等級精度と一緒ではありません。そもそも指しているところが違います。

ここでは、六角ボルトを例にして、現行JISで定義されている、「部品等級の違い」と「ネジ部の古い呼び方の等級違い」(現在はISOで記載すること)を解説していきます。
部品等級ABCは精度の違い
精度別(等級のABC)を簡単に分けると以下のような表にまとめることができます。これは生産上のネジ全体の仕上げ精度とネジ部の精度の組み合わせ違いになります。
| 部品等級 | 仕上げと公差 | ネジ部の等級 | ||
|---|---|---|---|---|
| ネジ部、座面の精度 | その他の部分 | 雌(メス)ねじ | 雄(オス)ねじ | |
| A | ◎高い(精) | ◎高い(精) | 6H | 6g |
| B | ◎高い(精) | △低い(粗め) | 6H | 6g |
| C | △低い(粗め) | △低い(粗め) | 7H | 8g |
ここには記載していませんが、「等級F」はM1~M3の小型精密用に属し、等級Aよりも精密になります。
JIS規格六角ボルトの種類(ABC)定義
JISの規格上では、等級AとBを首下の長さ別で分けています。Cは粗めに作る(仕上げる)場合なので、詳細には定義されていません。

| 種 類 | ネジの呼び径dの範囲 | 対応国際規格(参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ネジのピッチ | 部品等級 | ||
| 呼び径六角ボルト | 並目ねじ | A | d=1.6~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜以下のもの | ISO4014 |
| B | d=1.6~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜を超えるもの | |||
| d=27~64㎜ | ||||
| C | d=5~64㎜ | ISO4016 | ||
| 細目ねじ | A | d=8~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜以下のもの | ISO8765 | |
| B | d=8~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜を超えるもの | |||
| d=27~64㎜ | ||||
| 全ネジ六角ボルト | 並目ねじ | A | d=1.6~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜以下のもの | ISO4017 |
| B | d=1.6~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜を超えるもの | |||
| d=27~64㎜ | ||||
| C | d=5~64㎜ | ISO4018 | ||
| 細目ねじ | A | d=8~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜以下のもの | ISO8676 | |
| B | d=8~24㎜。ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜を超えるもの | |||
| d=27~64㎜ | ||||
| 有効径六角ボルト | 並目ネジ | B | d=3~20㎜ | ISO4015 |
表からでは首下長さでAとBがM径と首下長さで分かれるのが確認はできますが、頭の中で考えても分かりにくいので、具体的なネジ径で見ていきます。
等級のAかBかは、第一にネジ径で分かれ、次に首下の長さで分かれます。
ただし、ネジ径は実在する一般的な大きさがM20程度までとすれば、ほぼ首下長さだけで決まるものとも言えます。
部品等級AとBの違いは首下長さの違い
dはネジ部の直径にあたり、ネジの呼びである「M8」であればd=8mmです。このM8とM20で例に挙げると、等級AとBの違いは以下のようになります。
注意すべき点は「ただし、呼び長さlが10dまたは150㎜を超えるものと以下のもの」で違いがあります。これはM径(ネジ径)の違いで境界線が異なります。
M8(並目)の場合の等級AとBの境界長さ
- d=8 ×10=80㎜以下となり、M8(並目)の場合は80㎜以下が等級A
- 81㎜以上の長さはB等級
M20(並目)の場合の等級AとBの境界長さ
- d=20 ×10=200㎜以下となるが150㎜を超えるため、M20(並目)の場合は150㎜未満が等級A
- 150㎜以上の長さはB等級
六角ボルトのJIS規格サイズ
JIS B1180:2014
並目ねじ 等級A及び等級Bのサイズ一覧表
参考用に、JIS規格のネジ頭の大きさが分かるように、六角ボルトの対辺(工具のサイズ)と六角部の最大外形と高さを表にまとめています。
| M(呼び) | ピッチ | A六角 対辺 |
B外径 (最大) |
C高さ (基準) |
ネジ部首下に 定義がある範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.5 | 6.01 | 2.0 | 20~30 |
| M4 | 0.7 | 7 | 7.66 | 2.8 | 25~40 |
| M5 | 0.8 | 8 | 8.79 | 3.5 | 25~50 |
| M6 | 1 | 10 | 11.05 | 4.0 |
30~60 |
| M8 | 1.25 | 13 | 14.38 | 5.3 | 40~80 |
| M10 | 1.5 | 16 | 17.77 | 6.4 | 45~100 |
| M12 | 1.75 | 18 | 20.03 | 7.5 | 50~120 |
| M16 | 2.0 | 24 | 26.75 | 10.0 | 65~160 |
| M20 | 2.5 | 30 | 33.53 | 12.5 | 80~200 |
| M24 | 3.0 | 36 | 39.98 | 15.0 | 90~240 |
| M30 | 3.5 | 46 | 50.85 | 18.7 | 110~300 |
間違いやすいポイント
- M10の六角対辺は17mmではなく、JIS規格では16mm
- M12の六角対辺は17mmではなく、JIS規格では18mm
六角ボルトに工具を当ててみたら、「頭に入らない」「なんかブカブカして合っていない」となりやすいのが、このM10とM12のJIS規格サイズの頭です。
よくあるパターンは、手にもっていたメガネレンチが17mmだったという例です。
ネジ精度の旧等級とISOの比較

日本では「ねじの等級」として1982年で規定されたのが1,2,3級でしたが、ISOの国際標準化に切り替え、将来は廃止されることになっています。
| ネジ等級 | ISOの等級 | |
|---|---|---|
| めねじの場合 | おねじの場合 | |
| 1級 (並目) | 4H(M1.4以下) | 4h |
| 5H(M1.6以上) | ||
2級 (並目) |
4H(M1.4以下) | 6h(M1.4以下) |
| 6H(M1.6以上) | 6g(M1.6以上) | |
| 3級 (並目) | 7H | 8g |
| 1級 (細目) | 4H(M1.8×P0.2以下) | 4h |
| 5H(M2×P0.25以上) | ||
2級 (細目) |
6H | 6h(M1.4×P0.2以下) |
| 6g(M1.6×P0.2以上) | ||
| 3級 (細目) | 7H | 8g |
一般用のねじ等級として2級が多く用いられてきましたが、ISOでは、めねじ(メス)は「6H」、おねじ(オス)は「6g」を用いるように推奨されています。
これは、生産精度のABC等級とも混乱しやすいため、図面にネジ精度を記載する場合はISO規格を用いることが必要です。
六角ボルトJIS規格の等級まとめ
六角ボルトのJIS規格を見ても、専門用語的な種類や等級が数多く記載されているためよく分からないとは思います。用語を簡単に理解できるよう以下に整理しておきます。
- 等級のABCはネジ生産時の精度を表す
- ネジの精度は旧等級(1,2,3級)などで「級」として表していたが、現在はISOの6H,6h記載を推奨
- ナットの場合の種類(1種、2種など)は形状違いを表す
- JISは日本の規格でISOは国際規格、現在は国際規格に合わせるよう進んでいる。
この記事をシェアする
この記事の前後リンク
- 個人情報やプライバシーを侵害するような情報
- 閲覧される他の方に不快を与えるような内容や他の方に対しての暴力的な言葉や中傷
- 著作権の侵害・法律や倫理に反する行為
- 個人的に偏ったご意見や見解、他社を含む商品・サービスの不平や不満
- 個別記事の初期投稿日から一定期間を過ぎ、コメント投稿を受け付けていない場合
- 商品の感想または不具合など、個々に対応する必要がある案件
- 個々の記事に関係のない内容や話題の乱雑な投稿、迷惑なオフトピック
- その他、投稿時期のAI判別による不正防止と時事的な内容に抵触する場合など