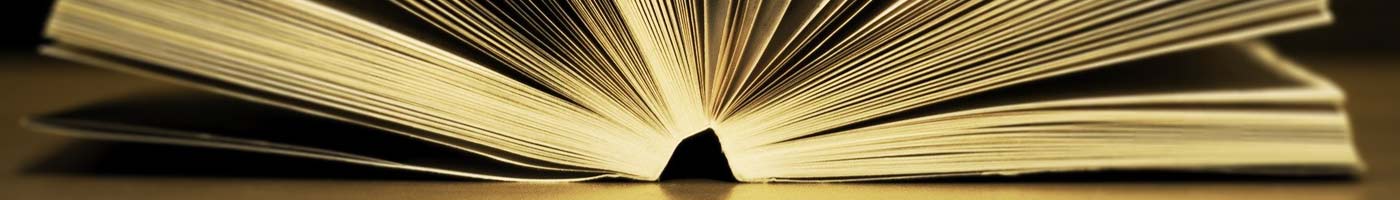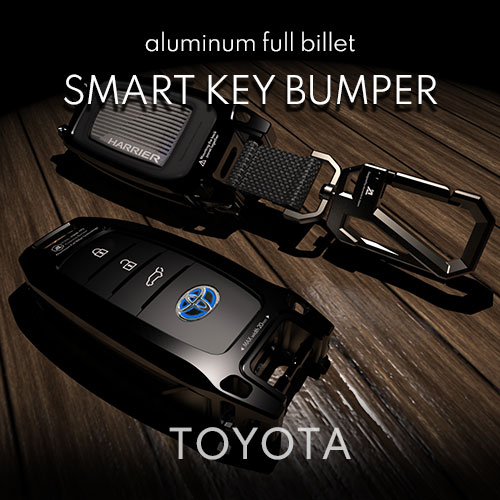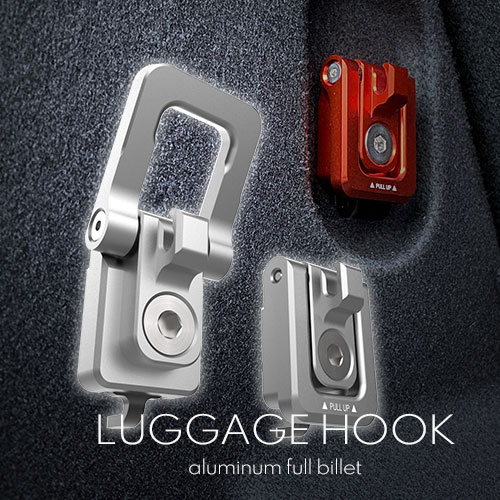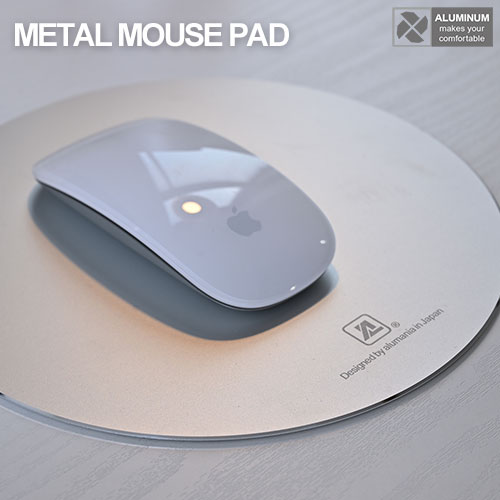本記事はアルミという素材について全般的に解説しており、常に加筆・添削しています。最後まで読むには5分以上を要します。
アルミはリサイクル性に優れた金属材料です。というのもアルミは鉱物「ボーキサイト」の状態から「新地金(しんじがね)」=アルミ素材の塊にするためには大量の電力エネルギーを必要としますが、それに比べ再生時(リサイクル時)は融点の低いアルミは溶かすエネルギーが少なくて済みます。
新地金(しんじがね)とは、
Weblioより引用
「ボーキサイトから作られたアルミナを中間素材に製造される新しい地金のことです。ボーキサイト約4トンから約2トンのアルミナ、2トンのアルミナから約1トンのアルミニウム新地金ができます。 」
アルミの場合は「新地金(しんじがね)」と呼ばれ、金属の地金(じがね)=インゴット(金の延べ棒)のような状態を指してもいます。

アルミの新地金を精錬(不純物を取り除いて純度の高いアルミに抽出)する電力に比べ、リサイクル(再生地金を作り出す)時は電力量が3%しか必要としません。そう聞くと新しい商品のアルミはほとんどがリサイクル?と思うかもしれませんが、日本で消費されるアルミは新地金が47%でリサイクルは53%ほどになっています。
日本では新地金の100%が輸入で賄われています。輸入元は南太平洋が多くオーストラリアやニュージーランドになります。二次再生(リサイクル)は日本国内でも行われますが、新地金は電気料金が安い国で精製される傾向にあります。
その純度の高いアルミに銅やマグネシウムなどの化合物をほんの少し混ぜることで、強度を上げたり耐食性を上げたりと用途に応じたアルミの性質を変えたものがアルミ合金になります。このアルミ合金は含まれる化合物や配合によってA5052などで知られる1,000番台での番号で分けることができます。
アルミ合金になるまでの過程
普段からアルミを材料として手にする加工前のアルミの板材やパイプの状態はアルミ合金になっています。そのアルミの合金になるまでには、鉱石のボーキサイト→アルミナ→新地金→アルミ合金(製品として加工する前のアルミ材料状態)になっていきます。

製品素材として利用できる「アルミ合金になるまで」の各過程を以下に順番に沿って解説していきます。
ボーキサイト

苛性ソーダ液で溶かして液体アルミン酸ソーダをつくり、そこからアルミナ分を抽出する
アルミナ

アルミナを溶融氷晶石の中で電気分解して新地金をつくります。ここに大きな電力が必要とされます。
アルミニウム(新地金)

この延べ棒状態に銅、マンガン、ケイ素、マグネシウム、亜鉛、ニッケルなどを化合してアルミ合金にしていきます。鋳造の場合はこのまま溶かして流し込むこともあります。
アルミ合金

合金にする際に板材や丸棒などへ次に加工しやすい形状にしたアルミの材料となり、その後に製品加工されていきます。
アルミのメリット・デメリット

メリットとデメリットに分けることは、それを逆に利用すれば逆転してしまう(デメリットはメリットにもなる)ため、ここでは一般的な観点でアルミのメリットとデメリットに認識される範囲で分けています。
アルミのメリット
- 軽い。比重が2.7(銅や鉄の約1/3の軽さ)
- さびにくい、耐食性が良い
- 熱伝導率がよく鉄の3倍
- 鋳造しやすい
- 電気をよく通す
- 塑性加工が簡単
- 鍛造性がよく、押出し加工でいろいろな断面形状に成形できる
- カラーアルマイトによる意匠性を見出せる
- シルク印刷、レーザー刻印が可能
- 再生(リサイクル)しやすい
アルミのデメリット
- 鉄やステンレスに比べると柔らかい
- 溶接で溶けやすいので難しい
- 厚肉となり他の金属よりも材料費が高くなりやすい
- 希少価値は低い
- 熱膨張しやすい
アルミのその他の特徴として
- 磁気を帯びない、磁石につかない
- 電磁を遮断しやすい
- 真空特性が高い
- 極低温(-200℃)でも強度が変化しない
- 光や熱を反射する
- 毒性がない
- 自然に酸化皮膜を作り腐食性が高い
アルミ合金の種類

その含有物によって素材番手があり、純アルミのA1070から最も硬い超々ジュラルミンのA7075まであります。(アルミの硬さ順で番号が高くなるわけではありません。)
頭のAはアルミの頭文字が付与されています。その次に数字4桁で詳細に分かれています。1,000の位で主となる含有物(主要添加元素)で分かれており、その元素の配合比率などの違いで下の位に番号が付いています。
アルミの合金は最初に「展伸用合金」と「鋳造用合金」に分かれます。
その展伸用合金は 【非熱処理型合金】 (#1000,#3000,#5000番手) と【熱処理型合金】 (#2000,#4000,#6000,#7000番手) に分けることができます。
アルミ合金記号(番号)の見方
詳細の含有物や含有量及び調質番号を詳しく知りたい場合は、「アルミ合金」Wikipediaの表をご覧ください。
展伸用合金の場合

①のAはアルミ。②の4桁の詳細は?
- 最初の1桁目(1,000単位の番号)で、新地金に配合する原料1~7に分かれます。(今のところ8まであります)
例では5番になるため、Al-Mg系です。 - 2桁目で基本合金「0」なのか、更に改良版かで番号が増えます。ほとんどは0です。
例では0のため、基本合金です。 - 3,4桁目は2桁(52など)で表し、アルミの純度の99%以下の小数点2桁になります。(99.00の00部分)
例では52になるため、99+0.52=99.52となり、意味としてはアルミの純度が99.52%ということです。
③加工方法
その次に加工方法(形状別)で板材ならPLATEのPや、押し出し材のBなどが付きます。(抜粋しています。もっと種類はあります)
- 「BD」=引き抜き棒
- 「W」=線
- 「H」=箔
- 「PC」=合わせ板
④調質番号
最後に調質(加工硬化や焼きなましなどで調整)の記号が―(ハイフン)の後に記載され、主には【非熱処理型】には「H」記号、【熱処理型】には「T」記号になります。 (抜粋しています。もっと種類はあります)
- 「O」=焼きなまし
- 「F」=製造のまま
- 「H」=加工硬化
鋳造用合金の場合

最初の【A】はアルミの意味で、その次に鋳造用の【C】かダイキャスト用の【DC】かの2種類です。鋳造用合金は展伸用と含まれる元素が異なっており、数字は【1~9】だけでなくダイキャスト用には【14】まであります。最後に含有量が細分記号として付与されています。
ダイキャスト用の材料番号は展伸用ほど詳細には分かれていません。また、展伸用でも―(ハイフン)以下は省略されることも多いです。
種類別(展伸用合金)特徴リスト

アルミの種類となると一般の方が利用する場合は展伸用合金になりますので、鋳物用は割愛し、展伸用合金の全体が掴みやすいように1,000番台別で表にまとめておきます。含有物、主に使われる身近なもの、簡易的な特徴でまとめておきます。
| 番手 | 添加元素 | 主な用途 | 特 徴 |
|---|---|---|---|
1000番台 A1070 A1050 A1100 |
シリコン・鉄 | 反射板 ネームプレート | アルミの素材純度が99.0%以上で不純物にシリコンや鉄が1%未満含まれます。 腐食性・加工性・溶接性・電気・熱伝導など多くの点で優れているのですが、なんといっても強度が低いため、深絞りに利用されやすい素材です。 |
2000番台 A2014 A2017 A2024 A2011 |
銅 | ゴム系の金型 リベット |
ジュラルミン(A2017)や超ジュラルミン(A2024)と呼ばれ、鋼材と同程度の強度が大きな特徴です。しかし、合金で銅を多く含むため耐食性が低くなります。アルマイト性も低くなります。 |
3000番台 A3003 A3005 A3105 |
マンガン | ラジエーター 電球の口金 |
加工性、溶接性、腐食性の高い1000番台の純アルミの特徴を確保しつつ、強度を高くしたアルミです。 |
4000番台 A4032 A4043 |
シリコン | ピストン 溶接棒 |
耐熱磨耗性に優れるため、摺動面があるものに用いられ、代表的なものはピストンになります。 A4043は5000番台以上のアルミの溶接棒として適しています。(3000番台以下はA1100) |
5000番台 A5052 A5056 A5083 A5454 |
マグネシウム | アルミホイール 船舶関係 | 日本で最もポピュラーなアルミがA5052 強度的には中程度ですが、加工性が高くアルマイトの発色性が高い素材です。板金製品はほとんどが5,000番台になります。切削にはA5056が適しています。耐海水性も高い |
6000番台 A6061 A6063 A6N01 |
マグネシウム シリコン | 窓枠 自転車のリム | 建築用に用いられることが多く、強度と腐食性に優れています。押し出し材はほとんどがA6063になります。 |
7000番台 A7072 A7075 A7N01 |
亜鉛 マグネシウム | スポークホイールのリム 航空機 | 超々ジュラルミンで有名なA7075はアルミの中では最高強度です。特に航空機で利用されることが多い高価なアルミ素材です。デメリットは腐食しやすいことです。 |
数字が4桁あることもあって、アルミの素材を伝える(呼ぶ)ときは「A7075」の場合、「エーナナマルナナゴー」と呼び、「えーななせんななじゅうご」と呼ぶ人は聞いたことがありません。電車の型式読みのような呼び方をしています。
アルミはどれを選んだら良いの?

鉱物からのアルミの地金までの流れ、含有物の違いでなど、アルミを製品の素材として利用するまでには様々な工程と、種類があることが分かっていただけたかと思います。
しかし、これだけ種類があるとどれを選んで良いか分かりません。
一般的に旋盤やフライス盤でDIY加工するなら、板材A5052Pと丸棒A5056Bを選んでいただければ、切削用のアルミ材料としては汎用性も高くアルマイトもできるので、最も扱いやすいアルミ素材であり、日本ではどこでも流通しています。

旋盤やフライス盤で加工時のおすすめアルミ
アルミの板材ならA5052P、丸棒ならA5056B
その他のアルミ素材については、その用途別に専門分野の中で利用されるものになるため、一般の方が選ぶということはまずありません。入手のしやすさからも国ごとで使用されるアルミの種類は変わります。
アルミの歴史は浅く最近の金属です

アルミはとても奥が深く、紀元前から利用されていた鉄などとは異なり最近の金属です。電気を多く使うこともあり、ほんの130年前からようやく精錬ができるようになって、徐々に生産量が増えて今では広く利用されるようになったものです。
生活の周りにはすでに数多くのアルミを用いた製品がありますが、数多くのメリットを持つ新金属のアルミは、これからも進化を続けて更なる価値も生み出していくであろう、多くの可能性を秘めた金属の一種でもあります。
この記事をシェアする
この記事の前後リンク
- 個人情報やプライバシーを侵害するような情報
- 閲覧される他の方に不快を与えるような内容や他の方に対しての暴力的な言葉や中傷
- 著作権の侵害・法律や倫理に反する行為
- 個人的に偏ったご意見や見解、他社を含む商品・サービスの不平や不満
- 個別記事の初期投稿日から一定期間を過ぎ、コメント投稿を受け付けていない場合
- 商品の感想または不具合など、個々に対応する必要がある案件
- 個々の記事に関係のない内容や話題の乱雑な投稿、迷惑なオフトピック
- その他、投稿時期のAI判別による不正防止と時事的な内容に抵触する場合など